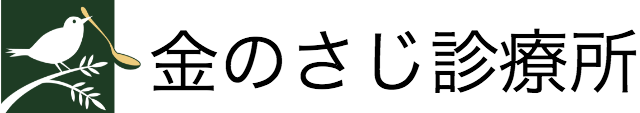今回の話は患者さん向けではないのですが、最近思ったことを書かせて頂きます。私が主催していうる勉強会で獣医さんと話をしているときに中医学を実践する上で難しい点はなにか聞いてみました。すると「たくさん症状があるといろんな可能性を考えて弁証(診断)がわからなくなる」という回答がありました。
私からすると症状がいろいろある方が弁証しやすいです。例えば刑事さんが事件の犯人捜しをするときに証拠はなるべくたくさんある方がいいですよね。もちろんその中には事件と全く関係ない物証もたくさん出てくると思いますが、ないよりあるにこしたことはないと思います。私にとってもっとも難しいケースは例えば健診で高血圧を指摘された。それ以外は極めて健康で何一つ症状はない、というような場合です。漢方治療は血圧計のように器械で測定して診断できるものではありません。診断するためには脈診や舌診ももちろん使いますが患者さんがどういった症状をお持ちなのかがかなり重要になります。
ただ、それで逆に混乱することがある、ということに私自身初めて気づかされたように思います。例えば頭痛を治療するときに実際にどのようなプロセスを経ているかというと、これまでの経験から頭痛の鑑別リストのようなものが漠然と頭の中にあります。とくに頻度の高い上位3つぐらいが意識せずとも頭の中にあって、その3つを診断するために必要な情報を問診票その他から探っていきます。その時にその3つの診断に関係しない症状についてはほぼスルーしていきます。そしてピックアップした情報から瞬時に3つの中でどれがもっとも可能性が高いかを判断し、それの診断についての質問をいくつかおこない、そこでほぼ診断がつきます。そうでなかった場合はその次に可能性の高い診断について同じように繰り返していきます。
このとき頭痛の診断に必要だった他の症状は中医学的には頭痛と同じ診断になります。つまりそれらは中医学的にみて繋がっている一連の症状であり、一つの薬でそれら全てを改善できる可能性があります。では頭痛の診断の時にスルーした症状はどうなるかというとそれは中医学的には別の診断になります。
時々患者さんから「私は東洋医学でいうとどのタイプなのでしょうか」と聞かれますが、血液型のようにこのタイプというのは難しくて、細かく診ていくと一人の患者さんでも複数の中医学的診断を持っていることが多いのです。例えば冷えるとトイレが近くなるのは通常腎陽虚で、肩こりからくる筋緊張性の頭痛が出るのは血液の滞りから来る瘀血のことが多いです。それに慢性的に胃もたれ、下痢しやすいのは胃腸が弱くて湿邪が溜まっている脾虚生湿という状態のことが多いです。もし一人の患者さんにこれらの症状がすべてある場合、中医学的にはそれぞれ別の診断になって腎陽虚、脾虚生湿、瘀血となり、処方もそれぞれ違ってきます。これを同時に治療しようとするとそれらをブレンドして処方することになります。(ちなみに私が普段おこなっているのがこれです)敢えて言うならこの中である程度体質と言えるのは腎陽虚と脾虚臍湿でわかりやすく言えば冷え症で胃腸が弱い体質ということです。
話がそれてしまいましたが、患者さんがいろんな症状を持っている中でそれをうまく診断に結びつけていくのは難しいのだなと認識しました。これに対する自分なりの解決策はあるのですが、話が長くなるし、一般の方には必要ないので書きません。ただ一つだけ要点を言えば一つ一つの症状について真摯に向き合い、深く分析することです。それが出来ればどのように症状を組み合わせるか、取捨選択するかが自ずとわかってきます。